若林地区でもう一ケ所目についたところがあり、
調査しました。
最初に調査した通りより、海に近い場所です。
重量鉄骨造で外壁がALCの店舗や、
RC造の専用住宅が残っていました。



ここまで調査をしてきて、
わかったこと。
それぞれ、地域毎に、津波の強さはかなり違いますし、
全壊するかどうかは、波を遮る遮蔽物や、
その建物の周辺に強い構造の建物があるか?
たまたま、流された船や、
住宅などの物体が当たるか当たらないか、など、
かなり、運的な要素が大きく影響します。
しかし、確実に言えることは、
①築年数が長く、耐震基準の古い木造住宅。
②耐震基準の新しい木造住宅。
③軽量鉄骨造。
④外壁材料の厚く、頑丈な物。
⑤外壁下地に、構造用ごうはんなどを張った物。
⑥重量鉄骨造
⑦RC造....
など、
一般的に、構造強度が高いであろうと思われる順に、
見事に倒壊や被害が大きいと言う事です。
当たり前なのかもしれませんが、
その事実を、この目で確認することが出来ました。
被害が小さかった、
といっても、2階の屋根まで、津波を被り、
鉄骨の建物すら傾き、
かろうじて原型ととどめている程度の状態の建物は、
引き続き使えるものはほとんど無い考えられます。
そういったとき、果たして、
コストアップを許容して、
一か八か、なるべく構造的に強い建物を
建てることにどういった意味があるのか?・・・
考えようによっては、
どうせ住み続けられないのならば、
なるべく簡素で安い構造にするべきなのか?・・・
それを考えながら調査を続けました。
一つ出た答えは、
やはり、それぞれの住まい手の、
経済状況や、思いの許す限り、
なるべく構造強度の高い物を作る意味は
ある。
もし、住み続けられないとしても、
躯体が残っていれば、
その後の生活にとってかけがえの無い、
思い出の品や、貴重品は残るかもしれない、
運良く1階までの浸水ならば、
逃げ遅れても、2階避難すれば助かるかもしれない。
。。。
住まいは、住むためだけの箱でなく、
思い出をしまう箱でもある。
そういった確立の積み重ねが、
命を救う確立にも重なってくるのだろうと。
あくまでも、経済的な縛りの中ですが、
なるべく、コストを抑え、
強い住まいを提供できればよいなと思いました。
ホームページが出来ました。
http://sheap.jimdo.com/よろしければお立ち寄りください。
ブログランキングに参加しています。
↓よろしければクリックをお願いいたします。
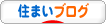 にほんブログ村
にほんブログ村
ありがとうございました。

 住宅| 浜松市|
住宅| 浜松市|